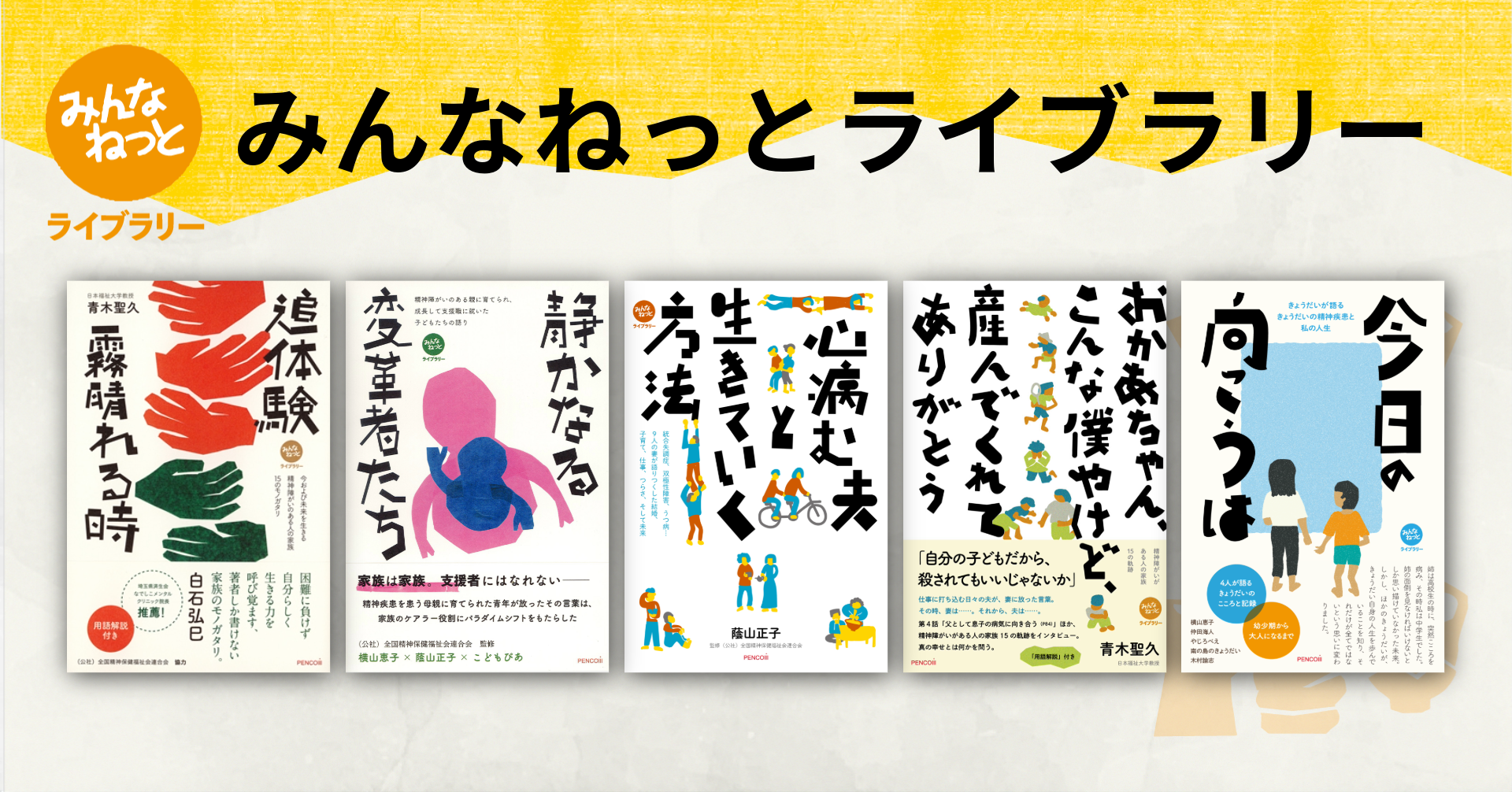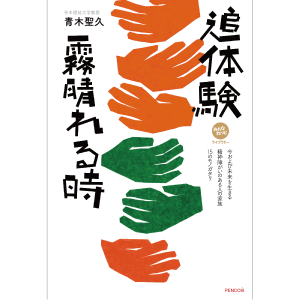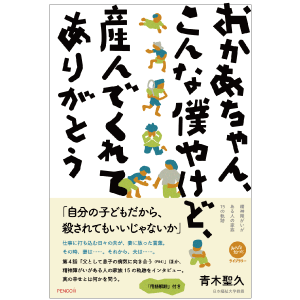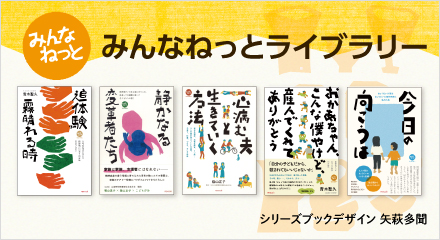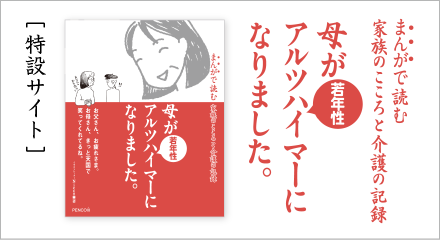生活保護と高次脳機能障害 家族の20年を思うー特定行政書士 三木ひとみさんの連載から
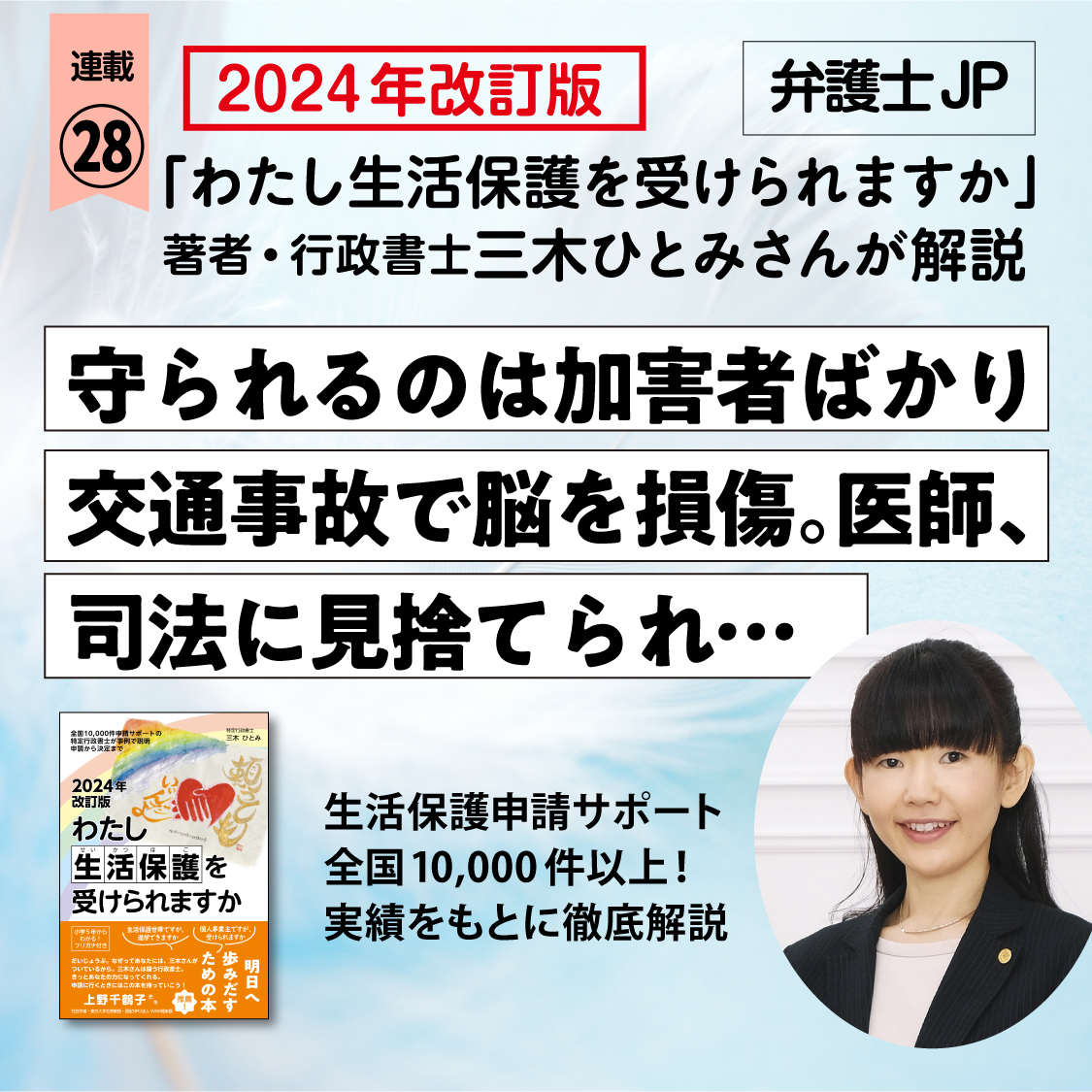
交通事故で高次脳機能障害に――「生活保護」が支えた親子の20年とみんなねっとライブラリーが伝える現実
弁護士JP連載で描かれた、母と息子の生きる物語
『2024年改訂版 わたし生活保護を受けられますか』の著者で特定行政書士の三木ひとみさんが、弁護士JPで連載中のコラム第28回【「守られるのは加害者ばかり」交通事故で脳を損傷、“生活保護”を頼った息子と母の20年】で紹介したのは、交通事故で高次脳機能障害を負ったユウタくん(仮名・当時19歳)と母マリコさんの歩みです。
▶ 記事はこちら:https://www.ben54.jp/news/2558
ある日、突然の事故で、親子の人生は変わりました。約20年前、大阪市在住のユウタくん(仮名・当時19歳)は、信号もない道をいつものように原動機付自転車で走っていました。すると、ウインカーも出さずに突然車が左折してきて、巻き込まれ、引きずられました。
その後待っていたのは、高次脳機能障害を負った被害者をさらに傷つける、終わりの見えない試練でした。保険会社も、医師も、司法さえも、「詐病だ」「精神的なものだ」と疑い続け、心ない言葉を浴びせました。知り合いからも「あの子、詐病で金を狙ってるんちゃうの?どこが悪いん?」などと何度も言われました。
そんな中、すべてを無条件に受け止め、支えてくれたものがありました。それが、「生活保護」です。経済的に困窮したときに申請できる、最低限の生活を保障するための仕組みです。事故の痛み、制度の冷たさ、世間の偏見、それでもなお暮らしていけるように、最後に残された命綱でした。
ユウタくんの母・マリコさん(仮名・当時40代)は「もしこの制度がなかったら、きっと息子と一緒に生きることをあきらめていた」と振り返ります。
「見えない障害」への偏見と孤立
高次脳機能障害は見た目では分かりにくく、医師や保険会社、司法までもが「詐病ではないか」と疑いました。知人からも心ない言葉を浴びせられ、精神的にも経済的にも追い詰められます。
あまり耳慣れない「高次脳機能障害」とは、どんな障害なのでしょうか。
日本福祉大学の青木聖久教授の著書『追体験 霧晴れる時』今および未来を生きる 精神障がいのある人の家族 15のモノガタリ(ペンコム刊)にも、高次脳機能障害と診断された青年の話が掲載されています。
博さんは、フィアンセの亜紀さんを助手席に乗せ、職場へ向かっていました。
午前7時25分――その時、悲劇が起こります。
交通事故に遭い、車は大破。亜紀さんは軽傷で済みましたが、博さんは意識不明の危篤状態に陥りました。
母親の恵子さんは、毎日病室を訪れました。しかし、博さんの意識が戻ることはありません。それでも、わずかな望みにすがり、手を握りながら声をかけ続けます。
「博、いつまで寝てるの。仕事に遅れるよ」
そして、事故からおよそ2週間後、奇跡が訪れます。博さんが恵子さんの手を握り返したのです。
慌てて医師に報告すると、「そんなはずはない」と首をかしげられましたが、それをきっかけに、少しずつ意識が回復していきました。やがて博さんは、言葉を発し、体も動かせるようになります。
ところが――。同級生の母親を指さし、「保険屋のおばさんだ」と言ったり、奇妙な発言や行動を繰り返すようになったのです。事故前の博さんとはまるで別人でした。
100日間の入院を経て、博さんは退院しました。
しかし、以前の面影はほとんどありません。子どものように振る舞ったかと思えば、急に怒り出す。便や尿の失敗も多く、匂いに鈍感になってしまったため、自分では気づかないこともありました。さらに、高級羽毛布団の契約をしてしまうこともありました。そんな日々が続く中、ある日、弟の卓さんがぽつりと漏らします。
「母さん、家に兄貴はいなくなってしまったね」
卓さんには、もうそこにいるのが事故前の兄ではないことを、受け入れられなかったのです。
同じく、青木先生の著書『おかあちゃん、こんな僕やけど、産んでくれてありがとう』精神障がいがある人の家族15の軌跡 P254には、用語解説が掲載されています。
【高次脳機能障害】
人には、食べる・怒る・泣くなどの、本能があります。それに対して、高次脳は、認識する・判断する・創造するというものです。
ところが、交通事故や頭部の負傷、脳卒中等によって、脳に損傷を受けてしまうことによって、高次脳に支障が継続してしまうことがあるのです。
これが、高次脳機能障害であり、日常生活においては、覚えられない(記憶)、気が散りやすい(注意)、動くことが面倒になる(自発性)というような部分に支障が出ます。
加えて、過度なこだわり、子どもっぽい行動(依存性、退行)、些細なことでの怒り(行動と感情の障がい)、金銭管理の困難さ等が挙げられます。
一方で、高次脳機能障がいは、法律との関係で言えば、精神障がいに分類されます。具体的には、2011年に「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準」が一部改正され、従来の「器質精神病」が、「器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)」というように、明記されるようになっています。
加えて障害年金も、認定基準を国が示した「障害認定基準」において、同様に明記されています(厚生労働省2017)。
生活保護から自立へ
三木ひとみさんの弁護士JPでの連載、28回目で取り上げられているユウタくんとお母様は、事故に遭い、脳を損傷し、高次脳機能障害に日常生活を奪われただけでなく、外見からは分かりにくい「見えない障害」への無理解ゆえに、詐病と言われどれほどつらかったことでしょう。
守ってくれると思っていた人や制度は、誰も守ってはくれませんでした。
「唯一、私たちを受け入れてくれたのは、生活保護だけでした」
マリコさんはそう振り返ります。生活保護は、最低限の生活を支える制度です。けれど、他のすべての救済から外れた人にとって、生活保護は絶望の中で唯一のよりどころです。
今、ユウタくんは生活保護を受けていません。障害と向き合いながらリハビリに通い、就労支援A型の職場で額に汗して働き、月に10万円ほどを稼いでいます。社会保険にも入れず、生活は決して楽ではありません。これまでにも、働いたり、生活保護に頼ったりを繰り返してきました。それでも、今は自分の足で立っています。
「それでも、今は自分の足で立っています。」
この一文に救われる思いです。
そしてあらためて、生活保護や高次脳障害などについて「知ること」が偏見をなくしていくことだと気付かされます。
みんなねっとライブラリーシリーズにつきまして
「みんなねっとライブラリー」とは、公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと)監修のもと、生きづらさを抱える本人と家族、きょうだい、配偶者が安心して暮らせる社会をめざし、ペンコムが出版している一般向け書籍シリーズです。
これまでに、「家族」「こども」「妻」「きょうだい」の立場から、それぞれ異なる困難の現状とその乗り越え方、必要な支援などについて、当事者と研究者が執筆したシリーズを出版しています。
- 『追体験 霧晴れる時』 今および未来を生きる 精神障がいのある人の家族 15のモノガタリ
- 『静かなる変革者たち』 精神障がいのある親に育てられ、成長して支援職に就いた子どもたちの語り
- 『心病む夫と生きていく方法』 統合失調症、双極性障害、うつ病… 9人の妻が語りつくした結婚、子育て、仕事、つらさ、そして未来
- 『おかあちゃん、こんな僕やけど、産んでくれてありがとう』
精神障がいがある人の家族15の軌跡 - 『今日の向こうは』きょうだいが語るきょうだいの精神疾患と私の人生
統合失調症、双極性障害、うつ…生涯を通じて5人に1人がこころの病気にかかるともいわれています。(厚労省みんなのメンタルヘルス)
同シリーズを通じて、家族、当事者、医療、福祉、介護、研究者など、多方面の著者が執筆し、分かりやすく、広く「こころの病」について理解を深めていただきたいという願いを込めています。